- 2020年6月に公布された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(サブリース新法)によって、サブリースの誇大広告や不当勧誘が規制され、サブリース事業者はそのルールに則って勧誘や契約内容の説明を行っています。しかし、賃貸不動産を新たに相続したり、新たに不動産投資をする方にとっては馴染みが薄く、内容をよく理解しないまま契約をしてしまうケースが散見されますので、サブリースを検討する際の注意点をまとめてみます。

1.サブリースの仕組みとメリット
サブリースの仕組みは、サブリース事業者がオーナーの物件を借上げるマスターリース契約(特定賃貸借契約)と、サブリース事業者が借上げた物件を入居者に転貸するサブリース契約(転貸借契約)の二つから成り立っており、二つの契約の差益がサブリース事業者の収益となる仕組みです。以下表にて、メリットを4点挙げてみます。参考にしてみてください。
|
メリット |
コメント |
| 1 |
収益が安定する |
賃貸経営をしていれば、家賃滞納者が出たり空室が発生したりして、得られるはずの賃料が入ってこないことがあります。サブリースであればそれらに関係なく一定の賃料が得られるため、経営の計画が立てやすいと言えるでしょう。 |
| 2 |
金融機関から建築費用等の融資を受けやすくなる |
サブリース事業者が作成した事業計画をサブリース事業者自身がプロとして事業運営するため、収益予測の確実性が増し、ローン返済の見通しが立ちやすくなります。 |
| 3 |
細かい経営判断をサブリース事業者に任せられる |
賃貸経営は賃貸人の判断が必要な場面が多く、急ぎの判断をしなければならないこともありますが、サブリースであれば常に電話やメールを気にする必要がなくなります。 |
| 4 |
トラブルの当事者にならずに済む |
最近、入居者とトラブルになったオーナーが深刻な事件に巻き込まれるニュースを見聞きしますが、入居者との賃貸借契約の当事者はサブリース事業者のため、万一の紛争の際にも当事者にならずに済みます。 |
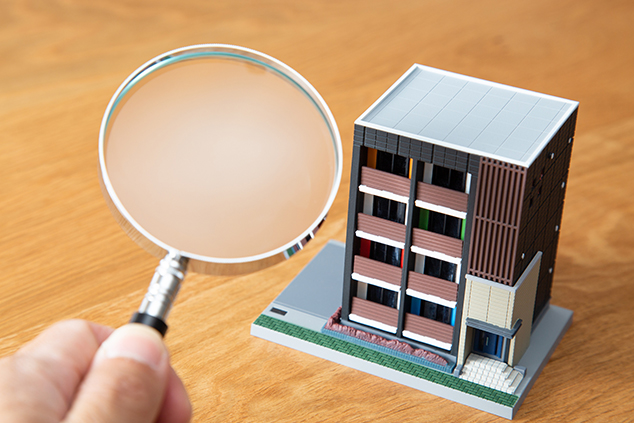
2.サブリースのデメリット
サブリース方式にはメリットがある半面、デメリットもあります。サブリース新法では、メリットのみを伝えて勧誘する行為が禁止されています。
事業経験の浅いオーナーがよく理解せずに契約しがちなデメリットを、同じく以下表にて4点挙げてみます。
|
デメリット |
コメント |
| 1 |
マスターリース契約の家賃は減額となる可能性がある |
借地借家法第32条には「建物の賃料が、租税その他の負担の増減、土地・建物の価格の上下、その他の経済事情の変動により、または相場の変動により近隣の同種の建物の賃料に比べて著しく不相当となったときは、賃料増減請求権が認められる」という規定があります。マスターリース契約ではオーナーが賃貸人、サブリース事業者が賃借人となるため、契約期間中や契約更新の際に賃料減額請求をされる可能性があります。 |
| 2 |
契約期間中でもマスターリース契約が解除される可能性がある |
マスターリース契約書の条項に、サブリース事業者から解約することができる旨の規定がある場合には、賃料減額請求があり折り合いがつかない場合等に、サブリース事業者側から契約解除できてしまいます。 |
| 3 |
オーナー側からマスターリース契約を解除したい場合に、正当事由が必要になる |
借地借家法第28条はいわゆる立ち退きに関わる条項ですが、マスターリース契約ではオーナーが賃貸人、サブリース事業者が賃借人となるため、オーナー側に正当事由が必要となり、簡単に解除できないということになります。 |
| 4 |
原状回復や設備の修理・交換費用、建物の修繕費用は原則オーナー負担 |
マスターリース契約書の条項にこれらの費用がオーナー負担と記載がある場合は、修繕等が発生した場合に毎月のマスターリース賃料から差し引かれて支払われます。 |

3.サブリース方式をうまく活用するためには
サブリース方式は、きちんと理解して活用できればとても便利な仕組みです。しかし、世の中で発生しているトラブルの大半は、オーナーが賃貸経営のリスクやマスターリース契約書の内容を十分理解しないままに、契約締結していることから発生しています。
サブリース方式も一般の賃貸も、収益の源泉は入居者が支払う家賃であることには変わりありませんので、賃貸経営がうまくいくためには、そのエリアのニーズに合った物件が相場の賃料で提供されていることが大前提となります。オーナー自身でも不動産ポータルサイトなどを見て市場性を調べるべきでしょう。
また、賃貸住宅は新築当初は入居者が決まりやすいですが、築年数がある程度古くなってくると決まりにくくなってくるため、家賃を下げて募集するのも一般的です。賃貸経営は長期間行うものなので、事業計画に値下がりリスクを織り込んでおく必要があります。
さらには、賃貸経営をうまく行かせるためには大小の修繕が欠かせませんので、事業計画にその修繕費用を見込んでおかなければなりません。退去した後のリフォームをきちんとしなければ次の入居募集が難しくなりますし、エアコンや給湯器などの設備が故障した場合には修理や交換が必要となります。建物の大規模修繕も、10~15年周期で実施しなければなりません。
サブリースの仕組みをうまく使うには、これらをオーナーがきちんと理解することが重要です。
サブリースは魔法の杖ではなく、基本の考え方は一般的な賃貸経営と変わりません。そのことに留意しつつ、事業計画書やマスターリース契約書の内容を精査し、契約締結へと進めるようにしてください。
公認不動産コンサルティングマスター、CFP®
独立系の賃貸管理会社ハウスメイトマネジメントに勤務し、賃貸仲介・管理業に20年従事。現在は不動産の利活用や相続支援業務を行っている。金融機関・業界団体等での講演多数。
※ 本コンテンツは、不動産購入および不動産売却をご検討頂く際の考え方の一例です。
※ 2023年3月29日本編公開時の情報に基づき作成しております。情報更新により本編の内容が変更となる場合がございます。